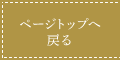彼らは本能のナビ(GPS)を持っている
- ワダ:
- 今回のクエストカフェ・インタビューは、ドキュメンタリー映画「タイガからのメッセージ」の監督、三上雄己さんに登場いただきました。今日はありがとうございます。
- 三上:
- はい。よろしくお願いします。
- ワダ:
- 実は、いつも雄己、ロビンという間柄なので、いつものように、雄己でいきたいと思います・・・笑
- 三上:
- 気楽な感じで行きましょう。。。笑
- ワダ:
- 雄己はいろんな活動してるけど、肩書きって好きじゃないんだけど、どういう活動をしている人って言えばいいんだろう?
- 三上:
- そうだね〜・・・一番長くやってるのがアーティストだから、アーティストっていうのが、一番しっくりくるかな・・・
- ワダ:
- なるほどね。それで、現在、力を入れて活動しているのが、極東ロシアのタイガ地方の先住民の人々の暮らしや生き方を取材したドキュメンタリー映画『タイガからのメッセージ』だよね。
- 三上:
- そうね、タイガというのはロシア語で、広く森っていう意味もあるし、北方の森っていう意味もある。
- だから、カナダでもタイガっていう呼び方をしていたりするけど、元々の語源はロシアからきているんだよね。
- ワダ:
- この映画を見て感じたことは、森や大自然、そして、先住民の人たちの暮らしがとても臨場感やリアリティをもって伝わって来たってことだね。
- 大自然の中に、猟師さんと一緒に自分が入っていくようなリアルな感覚がすごくあって、彼らの暮らしが身近に感じられたことかな。
- 三上:
- それは嬉しいね!このドキュメンタリーは、極東ロシアという地方で、ロシアの中でも一番東側を極東ロシア地方と言うんだけど、先住民ウデヘが狩猟採集を行っているエリアなんだ。このエリアは伝統的な狩猟をしていいというテリトリーを指定されていて、それ以外の場所での狩猟は違法になってしまう。
- ワダ:
- そうなんだ。
- 三上:
- やっぱり鉄砲撃つにしたって、狩りをするにしたって、ライセンスがあってやっているところもあって。ただ狩猟採集を先住民族がずっとやっているから、彼らはライセンスっていうよりも、ウデヘっていうのがライセンス。先住民族だからやっているというね。
- ワダ:
- 資源開発による環境破壊や経済至上主義的なものに、この希少な手つかずの素晴らしい自然や暮らしも徐々に犯されつつあって、その中でも、頑張って伝統的な暮らしを守ってきている人たちなんだよね。
- 三上:
- そうだね。
- ワダ:
- アイヌとかの人たちとルーツが同じということで、極東にはかなり広範囲に、アイヌ系の人々が暮らしていたみたいだね。
- 三上:
- そうだね、彼らが太古に日本に渡ってきて、ミックスして日本人が出来上がったという・・多分そういうルーツだと思う。
- ワダ:
- 他のエリアの人たちは別の名前があるの?
- 三上:
- 全体的にはロシアの北方先住民族っていう枠の中にいる人たちで、今だいたい40くらい残っているといわれている。その中のひとつがウデヘっていうんだよね。
- 村にも、実は14くらいの民族がいて、ウデヘが中心で、ナナイっていうのがいたり、オロチっていうのがいたり、チュクチっていうのがいたり、まあいろいろ・・・。
- 例えば、カムチャツカ半島にはチュクチっていうのがいたりとかね・・・。
- ワダ:
- オロチって人たちも狩猟をやっているの?
- 三上:
- うん、微妙に違っていて、あそこではウデヘとナナイが人数的には中心的なんだけど・・
- 例えば、ウデヘは狩猟採集で獣を槍や弓で突いて穫る。
- ナナイっていう人たちは川辺に住んでいて、魚を捕る漁が中心だね。
- ワダ:
- 映画の中で、川の人たちと森の人たちが出ているけど、あれはどういうこと?
- 三上:
- 今は両方やっているよ。でも伝統的にはウデヘはどっちかというと狩猟で、ナナイは漁労民族だった。
- ナナイは魚を取る人たちだから、定住型で刺繍の文化が発達した。
- ウデヘは狩猟採集が中心だったから、テントを張って、ある一時期だけそこの地域にいて、そこの動物の頭数が減ったり、枯渇してきたら、場所を移してまたテントを張って・・・って森の中を移動していったんだよね。
- それは本当に昔の話だけど・・・ソ連になってからは定住させられたから・・・。
- ワダ:
- 言葉も失われた。
- 三上:
- そう。
- ワダ:
- そのへんの話も少し出ていたね。ウデヘの言葉って残っているの?
- 三上:
- 映画の中で一生懸命歌ってもらっているおばあちゃんがいるんだけど、あれもやっぱり生きている人たちの中で、既に3人しかいない。
- 最後に出てきた77歳のリーダーのおばあちゃんがいたんだけど、映画が完成して2012年5月にウラジオストクに持って行って上映したとき、その三日前に亡くなっていたことを聞かされた。
- ワダ:
- そうなんだ。
- 三上:
- でも村の人たちは『おばあちゃんの歌をこうして録っておいてくれて、本当にうれしい』って言ってくれてね。
- そういう意味で、ウデヘ語っていうのは喋る人がどんどん減っていて、アイヌ語と一緒で口語でしか伝承されない。口語伝承だったから、ソ連化を強要した時に、言語は抑圧されて、シャーマニズムも抑圧したので、一回全部途切れたの。
- ワダ:
- アイヌみたいな刺青の風習とかあるの?
- 三上:
- どうだろう?刺青は見ていないな・・・もしかしたらあるのかもしれないけど、そこは途絶えてしまってると思うな、我々は見ていないね。
- ワダ:
- 映画の中で一番不思議だなと思ったのは、猟師する彼らと森の中の川をどんどん奥深く入って行き、上陸して、さらに森の中へ奥深く入っていくじゃない。
- 道もないのに、どうやって舟の場所まで帰ってくる道を理解しているんだろうって。僕らだったら、一瞬で迷子になるね。。。
- 三上:
- 獣道はもちろんあるし、猟師の道もあるんだけど、でも草や木が一気に芽吹く季節は本当に道がなくなる。彼らの体の中には野生動物が持ってるようなGPS(ナビ)があるらしく、それは本当は誰でも持っているんだけど、最初は驚いたね。右も左もわからないし、しかも、真っ暗な夜入っていくわけだから。
- ワダ:
- そうだったね。
- 三上:
- しかも、彼らは一人で狩りに入って行くし、トラもいるし、どういう感覚で入っていくのかなって、すごく不思議だったし、びっくりしたよ。
- でも俺たちも、何度も何度も彼らについて森に入って行くことによって、自分たちの中にある森と共生していた頃の自分たちの祖先のDNAなのか、細胞が覚えているのか、それがだんだんと活性化してきて、少しずつ方向とかがわかるようになってくるんだよね。そうすると迷わなくなって、大体わかってくる。
- ワダ:
- 彼らは小さな頃からそれをやっているから、当たり前なんだね。
- 三上:
- そうだね・・・それよりももっとすごいのは川だね。ビキン川っていうのが映画に出てくるんだけど、あれは支流がすごくて、上からみると、血液の毛細血管のような形になっていて、そこが湿地帯になっているんだけど、どんどん小舟に入って行っては狩りをする。それが「よくこの道を覚えているな」っていうくらい。彼らは本当にすごいよ!(笑)

失われた伝統は簡単には戻せない
- ワダ:
- 極東の大都市は、ハバロフスクとか、ウラジオストックだけど、彼らはそういう街に出てきたりもするの?
- 三上:
- もちろん。大学とかはそういうところに行かざるを得ないから、そこに行って勉強して。女の子なんかは帰ってこない子もいるしね。
- ワダ:
- 映画の中でも出ていたね。田舎は面白くない的なね。時代が変わってきたというのか、残念な気もするけど。
- 三上:
- それは日本の地方の過疎化と一緒だね。
- ワダ:
- アメリカのネイティブとか、自分たちの文化を復興したり、守っていこうとするのが盛んだけど、そういうのはないの?
- 三上:
- ソ連時代は、ソ連化っていうことで、言葉や文化が完全に抑圧されてしまった。1991年にソビエト連邦が崩壊し、ロシアになって、その時に先住民文化っていうものも一応存在を認められたのね。
- だから、ウデヘ語をしゃべることも解禁されたし、シャーマニズムを語ることも解禁された。ところがシャーマンを引き継ぐ人がいなかったから、シャーマニズムを掘り起こす・・・ハワイとかネイティブとかもそうだけど復興活動っていうことになっちゃったんだよね。
- ワダ:
- 一度途絶えてしまったらやりようがないよね。
- 三上:
- そう。だから一生懸命本を書いて残している人がいるんだけど、その本を書いているのをヘルプしたのは、実は北海道大学の人。向こうの人は、ウデヘ語の本を出すっていうことはしていない。
- ワダ:
- 作家の人がいたよね。
- 三上:
- アレクサンドル・カンチュガさんっていう人で、あの人は子供の頃からウデヘ語を喋っていたので、まだ覚えている。
- でも書き言葉がないから、ロシア語で音を真似て書いて・・で、それをウデヘ語研究家の津曲さんていう北海道大学の教授が日本語に訳して出すっていう・・・笑
- ワダ:
- オロチとかナナイとか覚えやすかったけど、日本語と似たような言葉使っているの?
- 三上:
- いや、それは違うみたい。
- ワダ:
- 言葉自体は違うのかもしれないけど、音的に似ているなって思ったな。小さなグループであのエリアに住んでいて、言語が独立しているっていうのはすごく不思議だよね。
- 三上:
- もっと不思議なのもあって、ミャンマー、タイ国境の山岳民族なんかは、もっと小さいエリアで、全然違う言葉を使ってるからすごいよ。
- ワダ:
- ナショジオ(ナショナルジオグラッフィック)の顔とも言われているカナダの文化人類学者ウェイド・デイヴィスが、ナショジオの番組で素晴らしいドキュメンタリーをつくっているんだけど、彼は「言語がなくなっていくと、自然が崩壊していく」ということを言ってて。
- 例えば、南米のブラジル、アマゾン川流域には、昔は3000もの部族がいて、それぞれの言語があったらしい。それがブラジルが国家を作っていく中で、公用語であるポルトガル語をある意味で強要し、それぞれの部族の言葉がどんどんなくなっていって、それと森林が減っていくタイムラインや場所の比率、状況が一緒なんだって。
- 多分、小さな部族グループがあって、自分たちのテリトリーで、ここより先は他の部族の場所だから、これより先に行かないみたいな。
- 自分たちのエリア内の資源は有限だから循環させて、自分たちで守っていかなくてはいけない。他のエリアから奪っていくと戦いになるから、自分たちで守っていく。「その中で循環させて資源が守られている」っていうことなんだと思うんだよね。
- 三上:
- うん
- ワダ:
- メルギブソン監督の『アポカリプト』っていう映画があって、マヤ、中南米のあたりの先住民の物語なんだけど、アステカ文明の中支配者が弱い部族を支配していく、襲って捕まえては奴隷にして。
- 主人公の部族グループが狩りをしていて、そのテリトリーに別の部族がいるのを感じ取るの。でもここは自分たちの猟場だと、リーダーと若者たち5人くらいが隠れる。で、何かある時は戦うしかない。
- そうしたら、その部族がここを通してくれって頼むわけ。よく見たら子供もおじいさんも集落の人々みんなが来ている。それで、とりあえず通るだけだからって通すのね。それはアステカ人たちが襲ってきたので逃げてきているわけ。
- それ見た時に「ああ、やっぱりテリトリーっていうのはそうやって守られていて、お互いに侵さない領域ってあるんだな」って思ったことがあって・・・
- 昔はウデヘも、そんな暗黙の場所ってあったのかな?
- 三上:
- もちろんあったし、部族の中で彼らが大事にしていたのは、クランっていう、現代で言えば“氏”っていう、名前でグループを形成して、それは絶対に侵さないっていうのがあった。
- たまたまケンカがあったとか、何かの取り合い、殺し合いがあった場合、血の掟っていうのがあって、ウデヘの場合は、“殺してしまった相手の娘を貰い受けなければいけない”というものとか。
- いろんな掟があったと思うんだけど、争いごととか子孫を残すとか決まりを守るとか、色んなものが一緒になっていて、彼らも小さなクランで生活していたら、結婚は禁止になっていく。だから、外から血を入れなければいけない。そういうのを争い事がある時に、チャンスとして使うとかね。アイヌも血の掟ってあるけど・・・
- ワダ:
- うん。映像的にみると、どうしてもソビエト時代にかなり文化とか教育とか、ソビエト化されているよね。
- ライフスタイルとか、見た感じ、生活は普通にロシアっぽいじゃない。ウデヘ独特のものは、実質何パーセントくらい残っているのかなって。
- 三上:
- パーセンテージはわからないけれど、今回映画の音楽をやってもらっているのは、アイヌのOKIさんっていうミュージシャンで、彼に一緒にクラスニヤール村まで来てもらったの。
- 彼にアイヌっていう目線からウデヘを見てもらった時に、開口一番言ったことは『ウデヘはいいな。彼らは狩猟採集っていう文化をまだ持っている。俺たちはそれを禁止されたから』って。
- その代わりOKIさんをはじめ、アイヌの人たちは、音楽とか、言葉とか独特の文様などのデザインなどはなるべく残させるように、復興させるようにしているけれど、狩猟はもう戻ってこない。鮭も戻ってこない。熊を穫るとかなくなったよね・・・
- ワダ:
- 映画の中では、ウデヘは民族衣装みたいなの着ていなかったよね。
- 三上:
- 森林伐採への抵抗運動している時は民族衣装着てたんだよね。ハラ―トっていう衣装は普通に着ていた民族衣装なんだけど。
- ワダ:
- あ〜映像にあったね。
- 三上:
- ウデヘで、彼らの中に強く沁み込んでいるのは、狩猟採集。鹿、イノシシを採って、それ以外は、ソ連時代も狩猟は認められていて、ゴスプロムホーズっていう、その時の狩猟組合・・農業組合のソフホーズ、コルホーズみたいな・・・それがあるから、彼らは狩猟した肉とか毛皮とか、国が高く買い取るものもあって、その代り言葉とか宗教、シャーマニズムっていうものはダメ、ソ連はそういう宗教を認めていないから。国に忠誠を誓わせるためにそうしたんだと思うけど。
- でも一緒に生活してみると、狩猟っていう部分は5割くらい、やっぱり半分は伝統的なもの持っているなっていう感覚はある。
- ワダ:
- 半分ってかなりだよね。映画の中で動物を穫り過ぎたみたいな話が出てたけど、それはソビエト時代の話なの?
- 三上:
- それは今だね。何故かというと、昔は、鹿とかたくさん穫っても保存できないから、村の仲間たちで分けるしかなくて、そんな多くは穫らなかったけど、今は冷蔵庫や冷凍庫があるから。
- 若い猟師なんかは、毎回来るの面倒くさいからって、まとめて穫ってしまおうというのもあって。だから現代病でしょう。
- ワダ:
- そういのは残念だよね。 いわゆるタイガで、ウデヘが暮らしてるエリアからもっと内陸に入ったところも、あんな感じなの?
- 三上:
- このドキュメンタリーをつくるにあたって、なぜ、あのエリアを選んだのかというと、タイガが広がっていると言いつつも、手が入っていない部分というのは、実はほとんどなくて、手が入っていないのは、あの地図のエリアぐらいって言われているのね。
- ワダ:
- へ〜そうなの!?
- 三上:
- あの極東ロシアエリアにアムールトラが500頭。世界でもわずか2000頭って言われているから、その4分の1がいるってすごいことなんだけど。ソ連の時代から、あそこは良くも悪くも木材の伐採地域だった。極東地方以外、西側の東シベリア地区から中央、北シベリアっていうのは、石油、天然ガス、金、ダイアモンドが出る場所。
- だから、そのエリアっていうのは、環境活動、社会活動っていう名目で“守れ守れ”って言っても、絶対守れない場所。そこはもう人を殺してでも資源を得る場所だから。
- だけど、極東地方、沿海地方に俺たちが行って、映画を撮っても命の危険にさらされないのかというと、あそこは地下資源がないから。森林しかない。だからロシアの当局もそんなに目くじら立てない場所。
- あとは、そのエリアの一部は、ウデヘが伝統的狩猟テリトリーっていう形で狩猟をやれる場所として権利を持っているからずっとできる。それでも伐採会社は入ってくる。木はあそこで一番の天然資源だから。
- ワダ:
- 彼らは森を守っているんだよね。
- 三上:
- そう、じゃないと狩猟できないからね、トラも住めないし。
- ワダ:
- 木材の会社が入ってきて伐採するのは、選んで切るの?
- それとも全部切るの?やっぱりルールとかあるのかな。
- 三上:
- いやいや、乱暴な伐採会社っていうのは皆伐。完全にフラットにしちゃう。
- ワダ:
- マジ!え〜、それじゃ再生できないでしょう?
- 三上:
- うん、再生するには200〜300年かかる。でも普通の伐採方法っていうのは世界中その方法だから。
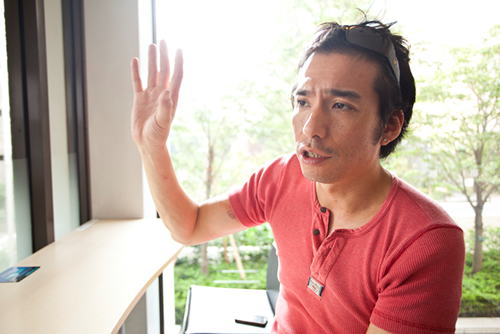
奇跡的に残っている伝統は、未来に残せる宝物
- 三上:
- ソ連の時と違って、ウデヘの文化を大っぴらに語れるようになった。ハワイの先住民、ローカル文化と近いところがあったから、それが俺の中で被ったんだよね。
- ハワイも1972年くらいまで全部禁止されていたからね。その後、そのローカル文化が出てきて、ハワイのシャーマン、カフーナの話、言葉っていうものが語られ始めた・・・それと一緒。
- ワダ:
- そうだね。ハワイのナイノア・トンプソンが、星や自然観察だけで遠洋航海する伝統的な公開技術を復活させてタヒチまでの航海を成功させた・・・あれがハワイの先住民の文化や民族復興のきっかけになったみたいだね。
- 三上:
- ホクレア号!
- ワダ:
- そういうのがひとつあったりすると、面白いね。
- 三上:
- うん、宣伝になったりとか、他の人が多く知るきっかけになったりするね。
- ワダ:
- 雄己たちが映画創らなかったら、なかなか日本の人が知ることはなかったしね。
- 取材に行って、ただカメラ回すだけじゃなく、彼らに向き合って撮影もしているだろうから、やっぱり伝わってくるものが違うんだよね。
- 三上:
- やっぱり、ちゃんと知ってもらいたいなっていう気持ちを持ってつくってるね。
- 彼らの生活とか生き方に、素晴らしいものを感じているからつくっているけど、彼らが持っているものを全部美化するつもりはない。
- 現代文明の中で、俺たちと同じ悩んでいる部分も試行錯誤している部分も間違っている部分もいっぱいある。
- 今地球上に住んでいる人間として、一緒に考えていきたいっていう部分があるから、現地での活動を一緒にやっているんだけど、その一部分としてあの映画があるんだよね。
- あの映画の着地点は、こういう生活をしている人たちがいます、だけど現代文明の波に呑まれて、彼らもすごく思い悩んでいます。そして村にはごみの山ができつつあり、村には新しい品物がどんどん入ってくるという物流も始まり貨幣経済に呑みこまれていく、若者も去ってしまったとか、文化も危うくなってくる。
- それは俺たちも経験していることでもあって、だけど日本ほど壊れていないっていう奇跡的に残っているものもあるから、そこをみんなで一緒に守っていくっていうのが、俺たちが未来に残せる一つの宝じゃないかなっていう気持ちもあった。
- ある意味でいいところを見せて、でも彼らの悩みも出して、自分たちのこの生活・都市生活と照らし合わせて考えて、自分事にしていってほしい、自分事にしていこうよっていうのがこの映画のメッセージだったんだよね。
- ところが3.11が起こっちゃったから、現代文明やばいじゃないかっていうのを突きつけられちゃった。
- ワダ:
- なるほどね。現代において僕が思うのは、生命体としての感性が弱められていき、どんどん無感覚になって、麻痺してきてしまっている。
- 例えば朝起きてきて、いつものように朝食を食べて、いつも同じ電車に乗って、会社に行って、一日を過ごして帰るっていうパターンを繰り返した時に、今日の自分は昨日の自分とは違うっていう感動を感じたりとか、自分の魂にエネルギーがみなぎって、本来の持ってるエネルギーが100パーセントではなくても、80パーセントくらいは活性しているかどうかみたいな、そういうことすら考えられない状況になっているというか・・・
- こうして生まれてきているのに、何か生命体になっていないというか、生きる屍というと言い過ぎかな・・ロボット化されているというか・・・
- そういう人たちが多数いるという状況の中で、今の社会がつくられてしまっているというのが、すごく違和感を感じるんだよね。
- だから政治のこととか、社会システムのことを“何で自分たちは、こんな世界に住んでいるんだろう”って思う時に、政治家はどうとか、社会システムをつくっている人たちがどうかとかっていう前に、自分自身がほんの少しずつ開かれていって、本来生きるっていうことへの意欲を取り戻すとか、そういった感性が開くようになれば、それだけで選ぶものが変わっていくじゃない。
- 三上:
- そうだね・・・
- ワダ:
- だから、映画の中で、そういう自分たちの中にある感性・・・彼らは伝統文化っていうものをもう一度取戻し、守っていくっていうのがあるけど・・自分自身の中の生きる力みたいなのを、もう一度甦らせるとか、気がつかなくちゃいけないっていう、今、分岐点のような気がするよね。
- 世界最大のトラ、アムールトラ、大きいのは体長3メートルにもなるんだよね。冬は、あのエリアは全部雪に埋もれるわけでしょう?
- 三上:
- 日本の豪雪地帯みたいな雰囲気ではないけどね。シホテアリニ山脈ってあって、その日本海側はすごく積もる場所があるらしいんだけど、クラスニヤール村は内陸側にあるから、そこまで雪が深くないからね。でも、冬はマイナス30度以下、夏は35度超の寒暖差が約70度の場所だから。
- ワダ:
- すごいね!そういうところで生き抜くわけだからすごいね、野生って。
- 三上:
- トラって、もともと南洋の動物なんだよね・・・だから、あの辺のエリアっていうのは、南方の植生と北方の植生が出会う場所なんだ。そこがある意味で奇跡的なのね。最後の氷河期の時に、凍らなかった場所って言われているんだよね。
- ワダ:
- へえー!
- 三上:
- いろんな植生が豊かにあって、トラも北はそこまで行けたんだよね。でも冬があるから、毛皮も南のトラより分厚かったり、脂肪分もあるしデカくなったんだよね。
- 多分、 アムールトラは、地球上に住んでいる個体の動物としては最強かもしれない。
- ワダ:
- でかいよね(笑)
- 三上:
- グリズリーベアとかと張るくらいの強さだよ。
- ワダ:
- たぶん、ライオンの倍くらいあるよね。
- 三上:
- あるある(笑)
- ワダ:
- トラと出会ったらどうなるの?
- 三上:
- 腹減っていれば襲う可能性もあるけど、トラも長い間そこの人間と一緒に暮らしているから、特に、人間の猟師とトラっていうのは対等って言われているよ。ある意味ライバルだね。
- トラが、一年間に鹿とかイノシシを穫る量って40頭って言われているんだよね。でも猟師もだいたい40頭って言われているの。だから、だいたい同じくらい消費しているって言われてる。もちろん、猟師は家族に持って帰るんだけどね・・・
- ワダ:
- じゃあ、トラは月に平均3、4頭食べるっていうことか〜・・・意外に少ないね。
- 三上:
- まあ、他のものも食べるからね。
- ワダ:
- なるほど・・・
- 三上:
- アムールトラと出会ったよっていう話を何人から聞いているけど、猟師がトラに出会った場合は、話しかけて、怒鳴って、怒って、トラとコミュニケーションした奴がいたりとか、ビビッて小屋から出られなかったっていう奴がいたりとか・・・
- ワダ:
- だってライフルで撃っちゃいけないんだよね?
- 三上:
- もちろん、撃っちゃいけない。
- ワダ:
- でも、命の危険にさらされて、ライフルを撃ったとしても、玉が効かないんじゃない?
- 三上:
- 急所だったら効くよ。効くけど、もちろん一発では効かないから、顔とかギュッて襲われた人もいたの。でも話によると、彼はトラを撃とうとしていたらしい。だから狙われたっていう話。
- トラは自分を狙っていない人間は狙わないって言われている。何故ならトラも一回人間を狙ったり、殺してしまったりしたら、自分も絶対ハントダウンされるって知っているから。
- それはウデヘの掟なの。人食いだったり、人間に手を出したトラはその日のうちに絶対に狩るっていう掟がある。
- ワダ:
- なんだかすごいね。
- 三上:
- お互いにわかっているんだよね、手を出しちゃいけないって・・
- ワダ:
- 攻撃しようとかそういう意図があればわかるんだね。
- 三上:
- そう、猟師なんかは殺める方でしょう。だから、やるかやられるかっていう微妙な間合いとかわかっているんだろうなって思う。
- だってね、村の連中の猟師は、もう村にいる時だと、本当にでろ〜としていてダメダメなんだけど(笑)・・
- 森に入ると全然違うからビックリする!目つきとか行動も変わる。
- ワダ:
- 映像観てたらそうだよね。酒は飲むの?
- 三上:
- 酒は飲まない。みんな30歳になったらだいたい酒を断つの。飲みはじめると底なしで、ウォッカを一人で空けちゃう。飲めちゃうから、どんどん飲んでアル中になって、それで身を崩した人もいるから、俺たちの世代はみんな止めている。
- ワダ:
- 面白いね。ぜひみんなに観てもらいたいね。みんなで観るっていうのがいいね。
- 三上:
- 後で、いろいろと話せると面白いね。

森との付き合い方が、文明に大きな影響を与える
- ワダ:
- 映画を撮るに至ったのはどういう経緯で?
- 三上:
- 基本的に、環境や社会問題に関しては、子供の頃から興味を持たされていたのか、興味を持ったのか、家族のこともいろいろあって・・・
- それで、アートや音楽を志したティーンエイジャーの頃は、そういった活動があまりにも近すぎて、それだけをやるのはつまらない。
- あとは、日本の活動家の人たちって、ハードコアすぎるのか、ちょっと普通の人っぽくない・・俺はそうは思わないけど、デモやってる人とかはちょっと怖い人なのかなとか、ちょっと変な人たちみたいに外部から見られているのはわかったし・・・
- 俺はそういうことに興味はあるから、アートや音楽を通じてそういうことをやるのはいいなって。U2のボノみたいなね・・。
- 自分のやりたいことは音楽だったから、10代〜20代前半の頃はそっちをメインにやっていこうと。
- ずっと海外が長くて、25〜26歳の頃に日本に帰ってきて、もう日本もNGOとか、スマートにやっているかなと思いきや、全然そうではなく社会と切り離されたところでやっていて、機能していないって思った。
- 機能しないのは社会も悪いけど、多分やっている人も違うことをやっているんだろうなって思ったから、そういうところから離れていたの。
- でも、2000年過ぎた頃に、世界でこれだけの人たち、環境、気候、生物多様性が危機だっていうことがどんどん言われてきているから、さすがに、企業とか社会も変わっていくだろうと思っていたけど、まったく変わらない世界が広がっていて・・
- 21世紀に入って、自分もその頃30歳を超えて、これはマズイなっていう気持ちが強くなって。
- 自分の仕事も、コマーシャリズムに乗ってやっているのが気持ち悪くなってきてしまって・・・
- 子供の頃から環境問題とか目の前にあったから、家の中ではリサイクルとか、無駄にしないとか当たり前にやっている自分がいても、仕事のうえで実践できないのね。コマーシャルとか映像制作の現場では、無駄が酷いんだ。弁当余ったら捨てるし、いらないもの買って、いらなかったら捨てるとか、倉庫入りしたり。それも、全部予算の中に組み込まれている訳でしょう。そんなことをしていたら、この世の中どんどん悪い方向にしかいかない。それだったらもう覚悟して、こういうのは辞めようって。
- 自分がやるべきだって思うことをやろうって思ったの。それはボランティアではなく仕事でやろう、じゃないと説得力がないし、自分も生きていけないと思ったから。
- 違う仕事でお金をいっぱい稼いで、ホリデイでボランティア活動をしましたっていうのは、きれいごとだと思うんだ。だってハッキリ言って機能しないから。
- 100個やったうちの1個だけいいことしても何も変わらないから。毎日毎日それをやり続けて、意識し続けないと、変わっていかないなと思ったからね・・・
- ワダ:
- なるほどね〜
- 三上:
- 2005年くらいからシフトしようって。
- じゃあ何をやろうって考えたら、俺はクリエイティブで生きてきたから、それを使った方法しかないって思って。
- 環境OGOのワークショップにどんどん参加して、今一番何がヤバいか現状を知ろうと思って。彼らは現場のデータを一番持っているから、世界で、日本で求められていること、今やるべきことをどんどんリサーチしていったんだよね。
- そうしたらあるチームが『雄己、森林のこと知っているか、森林って、今、大変なことになっているんだよ』って教えてくれたの。
- ワダ:
- うん。
- 三上:
- 森林って、ずっと伐採されているっていうのは知っているけど、何がどれだけ大変で、何がそこを司っているんだろうって話を聞いていった・・・
- 歴史を紐解いてくと、森林伐採、人間の森林との付き合い方がその時の文明にかなり影響を及ぼしていたっていうことを知ったんだよね。
- 環境考古学っていうのが盛んに出てきているけれど、例えば、ローマの崩壊は、ゲルマン民族の南下で促進されたと言われている。南下はなぜ起こったかっていうと、ヨーロッパ、今のフランス、ドイツのエリアが急激に寒冷化しちゃって、それでローマが崩壊した事実というのがある。森林を伐採しすぎて、イタリアの半島の木は全部なくなり、その結果、寒冷化が急激に起きたという分析が最近されてるんだ。
- 日本とは環境が違って、ヨーロッパ大陸では、伐るともう再生されない、生えない。砂漠化に向かっちゃうの。それで北上してフランスやドイツの木を伐り始めた。そのため小さな気候変動が起こったと言われていて、それが北ヨーロッパの寒冷化を生んで、その寒冷化によって、狩猟採取していたゲルマン民族は、耐えられなくなって南下してきた。それでローマの文明に入ってきて破壊をしたと言われている。でもそれは、ローマの人たち自身が起こしたことかもしれない。
- ギルガメッシュ叙事詩にも、十字史にも書いてある、森林破壊のお話があったりとか、あとはイースター島のお話で最終的には共食いになってしまったというのも、全部森の木を伐っちゃったから。
- あの時は貨幣経済っていうよりも、イースター島のシンボルを建てる競争に走ったわけだけど、あれを建てるために森林を伐採し、イチバンを争っているうちに崩壊してしまったとか・・・。
- 今、イースター島で起こっていたことと同じことが、地球規模で起きているんじゃないかなっていうのがあるかな。
- ワダ:
- 中世から近代にかけて、大航海時代にも、船を造るためにものすごい木を伐っているんだよね。
- 三上:
- そうそう。建築もそうだし。
- ワダ:
- ドイツのシュバルツバルト、黒い森っていうのは、あそこはもともと広葉樹の森だったらしいけど、自然の木々は全部切っちゃって、今は全部、人工の針葉樹の森になっている。
- 三上:
- そうだね。
- ワダ:
- 日本で宮崎駿の『もののけ姫』でさ、鉄の製鉄所で描かれている森は全部広葉樹で、あの舞台は島根県のエリアらしいんだよね。主人公アシタカは東北から南下してくる。
- ・・で、全然違う民族的な連中がそこにはいて、渡来人的な雰囲気で、主人公は縄文、アイヌ系の民族だよね。
- 三上:
- 森の民みたいな・・・
- ワダ:
- あの時に製鉄みたいなね、実際には石見銀山とか。それによって木を相当燃やした、全部それを針葉樹に変えたそうなんだよね。針葉樹は生えるの早いからね。
- 三上:
- 環境破壊の歴史の始まりっていうのは、森林から始まる。いまだに人間は森林を伐っては「ダメだ、それで環境が破壊されてしまう、だから何とかしよう」ということを人類史始まって以来、ずっとずっとやっているらしいんだよね。だけど1回も、森林破壊を自分たちで止められていない。
- それってすごいことで、ある意味今の状況を示唆しているんだよね。今はもう最終段階かも知れない・・その森林の状況を聞いて、俺は「これは森林中心にやってみよう」と。
- それで2008年くらいから森林の映像をやり始めて。まずは、森を調査している人たちに話を聞くところから始まったんだけど。
- 2008年から2009年にかけて『木の来た道』っていう50分のドキュメンタリー映画をつくったんだよね。それは、世界の森林、日本の森林、木材の話なんだけど。DVDも出ているんだ。その時に初めて、今の世界の森林の現状をかなり目の当たりにしたの。自分でも色々調べたからね。そうしたらタイガっていうのが出てきた。
- ワダ:
- そういう流れだったんだね。
- 三上:
- タイガが近くにある。しかも、すごく生物が多様であり、あまり触られていない森があるじゃないかっていうのを知って、まず、行ってみたくなった。
- 先住民の狩猟採集の生活とか、ロシアっていうのも行ったはことなかったから、ロシアも見てみたいって。近い割には、遠い場所でしょう。
- ワダ:
- そうだね。
- 三上:
- あと、実は、俺の父親が満州生まれで、おじいちゃんは広島の人、おばあちゃんは岡山で、その人たちは20年近く満州に住んでいたの。おじいちゃんは終戦直前に40歳で徴兵されて、ソ連国境に配置され捕まって、収容所へ・・・子供の頃にその話を聞かされていて。
- だから、俺にとっては、中国東北地方と今の極東エリア、シベリア、東シベリアは、小さい時から話を聞いている場所なんだよね。しかも、そこがタイガなんだよね。
- ワダ:
- なんか不思議だね。
- 三上:
- うん、何か呼ばれた感じもしたし、行くしかないないなって思って。
- ワダ:
- 雄己のこのワイルドさって、その辺からきているんじゃないの?
- 三上:
- アハハハ(笑)大陸文化っていうのは、そういう意味でのつながりがあったから・・小さい時から、おじいちゃん、おばあちゃんから聞いていて・・
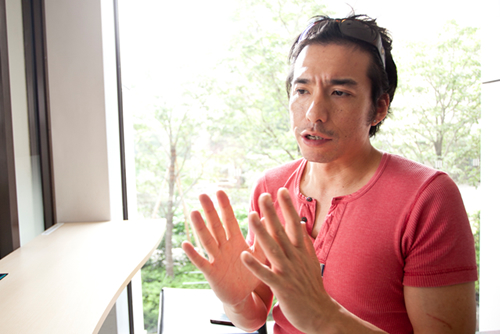
巨大なUFOが目の前に現れた
- ワダ:
- 雄己が子供の頃は・・フランスだったよね。
- 三上:
- 子供の時はフランスで、高校からイギリスだね。
- ワダ:
- 日本での暮らしってどのくらい?
- 三上:
- 小学校1年から4年までは日本だったし、中学校3年間行ってるし、あとは26歳までヨーロッパだった。
- ワダ:
- 日本の暮らし、全然少ないと思うんだけど(笑)というより、日本の文化よりも向こうの感覚だと思うね。お父さんやおじいちゃんの話もあり、その辺の運命的な流れっていうのも、日本の中から世界を視るっていうより、日本人としての雄己が、地球全体を見ている感じかな〜
- 三上:
- うん。
- ワダ:
- 地球全体を見ている感じって、子供の頃からあったんじゃない?
- 三上:
- あったね〜それはすごくあって、大人になるにつれて自分でも意識するようになった。それまでは意識していなかったけど、子供の頃から友達とつるんで話している時とかに、ズレを感じて、そのズレってわからなかったの。
- これは親がヘンなのかな、家の教育がおかしいのかくらいしか思わない。でも、どんどん自分の意識に入っていくことによって、もうちょと知ることになっていく。
- ワダ:
- なるほど、面白いね。 1年生から4年生、そこでまた、中学まで抜けることになるじゃない。そのギャップとか、違和感とか出るんじゃない?
- 三上:
- そう、逆にフランスに行った時って、言葉とかあまりわからないのに『ああ〜帰って来た、ラクチン』って思った。肌の色も全員違うし、文化も全員違うのが許される場所で。
- 日本に帰ってきたら、統一!みたいな感じで、体も心もビックリしちゃって、逆カルチャーショックが無茶苦茶強くて、それでもう本当にヤバい、俺がおかしくなるか、潰されるかって、早く出ないとって直感的に思って、高校から出るって決めて、その準備をしていた。
- ワダ:
- へえ〜。
- 三上:
- たぶん出なかったらマズイことになっていたと思う・・・
- ワダ:
- 話がぜんぜん変わっちゃうんだけど、前に話してくれたUFOの話。。。かなりぶっ飛んでるよね。。。笑
- 僕も、30機以上の編隊飛行のUFO見て、この世のものとは思えなかったんだけど、なんて言うかな〜・・・UFOって、今から50年とか60年前に、アダムスキーのUFOの話で、にわかに注目されるようになったんだけど、もっと昔は、いなかったのかなと思ったりするんだ。
- 日本でも、古文書とか、海外でも古い文献に不思議な光や飛行物体の話は出て来るみたいだけど、今メディア、ネットが発達してきて、どんどん露出してきているような感じがする。
- 多くの人たちが目撃、体験するっていうことがあって、スマホもそうだけど、そういうの記録しやすいし、メッセージもすぐに発信できちゃう。
- それは、みんなに準備ができてきてるから、そういう体験が起こるのかなって思ったり。
- 三上:
- それもあるし、それの感知、認知の仕方が変わっているのかもしれないって思っていて・・
- もしかしたら2、3千年前に見かけることはあったかもしれないんだけど、まだ地球という世界観に関しても狭い視野でしか捉えていなかったと思うし、全部が人間よりも大きな存在で、自然にも祈る、ひれ伏すしかなかったっていう原始時代。全部が神的みたいな。
- その時にUFOとか感知できないものを見た時に、今みたいに文献を残して、細かくは残せなかったんじゃないかって。
- ナスカの地上絵とか、洞窟に何か描いてあったりするけど、今の現代の人たちにはどれだけ伝わっているかはわからないなって・・・見ている人はいるんじゃないかな。
- ワダ:
- 自分たちがまったく理解できないものを見た時に、見えなかったことにするってあるみたいだよね
- 三上:
- うん、あるね。
- ワダ:
- 大航海時代に、未開の島に帆船が現れて、初めて帆船をみた先住民たちは、それが何か理解できなかったために、見えなかったとかっていう話あるね。よくわからないんだけど・・・
- 三上:
- そうそう。見たものが認知できないと何だかわからないから、もしかしたら幻かもって片づける。
- ワダ:
- UFOなんかも、UFOってこんなだよっていう具体的な情報があるから「これってUFO?」って思ったり、感じたりできる。雄己が見たのはロンドンだったよね。
- 三上:
- アパートから見えた。デカいのがゆっくり・・・UFOなんてあり得ないだろうと思っていたら、もしかしたら見えていなかったかもしれないよね。認知できなかったかもしれない。
- ワダ:
- とんでもない大きさ?
- 三上:
- そう、冗談みたいな大きさ!(笑)
- ワダ:
- 直径的には?
- 三上:
- わからないけど、自分のサイズ感で言えば、数百メートルくらいだよね。建物一個分のものが飛んでるの(笑)
- 大きさとしては豪華客船くらいの、形はアダムスキー的な。
- ワダ:
- グレーの・・?
- 三上:
- 鏡面っぽい感じ。
- ワダ:
- へえー。
- 三上:
- だから透明なのかなって、透けて見えるような・・
- 本当に透けているのかなって。
- ワダ:
- 周りが映り込んでいるのか、透けているのかみたいな感じ?
- 三上:
- そうそう!よくスタートレックで出てくるけど、どっかの次元から出てきた時に透明な感じじゃない。ちょうどそんな感じ。
- ワダ:
- 見たのはそれ1回だけ?
- 三上:
- うん。ちゃんとしたのはね。光の点だったら『あれ何だろう?』って思うけど、そんなんじゃないからね(笑)カタチもはっきりしてるし。
- ワダ:
- その体験から変わったことってある?
- 三上:
- いや、変わってなくて。実はその体験よってコンファームされた感じだね。確信。思っていたことが更に具体的に、お前が思っていることは幻想じゃないぞっていう答えをくれた感じ。
- ワダ:
- なるほどね。僕も30機くらいの編隊を見た時っていうのは、見ている時はUFOって思っていなくて、ただ、何だろう?って。。。もう最後の数機が彼方に見えなくなるっていう時にあれ〜?っていう不思議な感覚で・・
- 最近、僕の周りで、UFOを見たことあるっていう人が、数人現れたので。しかも、みんな雄己みたいに体験がハンパないから・・・笑 探せばもっといると思う。
- 三上:
- へえ〜そんなに。。。!?
- ワダ:
- 少し前に、友人になった女性の経営者で、学生の時に秋田に里帰りして、普通にクルマが走っている街中で、彼女曰く、直径5キロほどの巨大なUFOが上空にあって。下はカラフルに電飾めいた感じで、クリスマスのように光っていて、キラキラしてたそうだよ。ゴージャスだよね。。。笑
- 周りには人もたくさんいて、クルマも走ってるのに、見て驚いている様子はなくて、家にカメラを取りにいって、外に出たらもういなかったって。
- 三上:
- うん。
- ワダ:
- もう一人は、新宿でね。防衛省が見えるマンションに住んでいて、ちょうど防衛省の真上に巨大な母船型のUFOがあって、たくさんの窓が3列に並んでいたんだって。
- 三上:
- 窓がついてるんだ(笑)
- ワダ:
- 豪華客船みたいに窓が並んでいて、その中に乗ったという。
- 三上:
- 乗ったの!すごいな(笑)
- ワダ:
- みんなそれでだからといって、人生が変わったというのではなくて、たまたま聞いてみたら私も実は・・みたいな。
- 三上:
- 俺は変わったっていうよりも、その頃は見えない力や感知できない何かっていう物には、気づいているというか、アートやっているわけだから、そういう力を信じていないとモノづくりはできないと思うんだけど、そういう物に対して、いいんだよ、そういうものはあるんだよっていう更なるコンファメーション。メッセージをもらったっていう感じだね。

なぜ、この地球に生まれてきているのかにミッションがある
- ワダ:
- 今後の活動の展開としてはどんな感じの予定ですか?
- 三上:
- タイガに関しては映画での活動もあるし、タイガに関する展示もやったり、もっと日本の人たちに知ってもらわなくちゃいけないって思っている。
- UFOと同じで、知らないと、もしくは認知してなければそれは「ない」と一緒。
- 例えば、知らない動物が、存在しないっていうのと一緒で、それが殺されていなくなったって後で聞いても、リアリティが全くないし、そうなんだ〜で終わっちゃう。なくなったことに危機感も何も感じない。
- でも、実はあるんだよ、ここにこんな人が住んでいるんだよ、こんな生活しているんだよ、日本の近くにあるよって。
- 映像だけでも知ってもらって、こうやって行った人間から体験を聞いたらリアリティも出てきて、ロビンも今回観てくれて「自分も行ったような体験をした」って言ってくれたから、すごく嬉しい。もうそう感じたら、そこにタイガがあるでしょう?
- ワダ:
- うん、あるある。
- 三上:
- あるっていうことがすごく大切で、そうしたら今度は、そこがなくなりそうになって署名してと言ったらしてくれるだろうし、何かヘルプしてよってなったら、何か考えてくれるじゃない。
- それを拡げていかなくちゃならないって思っている。それをひとつのミッションとして、今まだプロジェクトとして続いている。
- あとは映画監督、ドキュメンタリー作家として活動している部分があって、それがストーリーを伝える一つの方法として確立されつつあるから、今、何点か企画を練っているのものもあるし。
- あとは、映像というものの体験を、ただ観るものとしてだけでなく、インスタレーションみたいなこともやっているので、“映像と空間と人がいて”っていうものを、どれだけ面白い体験ができるかなって。
- カップルで、家族で、友達同士で来るっていう、エンターテイメントとしても楽しめるけど、そこで、もう一つ持って帰ってもらえるものを創るっていうのも、新しい遊び方のひとつかなって。
- ワダ:
- うん。
- 三上:
- 俺はもともと遊び大好きだしね。でももう空虚な遊びだけでは成り立たないところに来ている。70年代80年代のような、資源もある程度ある、人間もこれだったらあと3千年、4千年くらいは問題ないよ、生きていけるよっていう、楽観的に生きられる時代ならば、俺たち何もしなくていいかもしれないけど、もうタイムリミットが目の前に見えているような状態ならば、やっぱりそこに寄与しなければ、アートとかクリエーターとか言ってはいけないよね。
- それはやっぱり自分に課している。そういうところから社会がシフトしていくって。
- じゃあ何故この時代、危機の時代に生まれて生きているのかっていうところにミッションがあるでしょう。それをみんなで共有できて初めて、今の地球体験っていうのが、俺たちが死ぬ時に、ああやっぱり地球体験してよかったなって思えるんじゃないかって、思っているので、あと何十年生きられるかわからないけど・・・。
- ワダ:
- そこまで果たして地球環境、この世界を大丈夫かっていうのはあるよね、悲観はしていないけど。何か起こっても、そこから次のステージでは新しい地球っていうものがどんなふうになっていくのかなっていう部分で、寄与したいなって。
- 三上:
- うん。
- ワダ:
- ぜひいろいろ拡げていきましょう!
- 三上:
- ぜひ一緒に何かやりましょう!
- この出会いはすごく大切だと思っているので。
- ワダ:
- このインタビュー読んでくれている人や、クエストカフェに集まってくる人たちって、みんな同じエネルギーや役割を持っている人たちだなって思っているので。
- 三上:
- そうだね。
- ワダ:
- 今日は長い時間、ありがとうございました!
- 三上:
- こちらこそ、楽しかったです。ありがとう!
- * 制作協力 : 藤田明子
【取材後記】
昔からテレビでは、未開のエリアに取材班が入り、見たことも、聞いたこともないような場所やそこに暮らす人々、民族などを紹介する番組があった。
僕の子供の頃は、久米明のナレーションの「すばらしい世界旅行」や「知られざる世界」「驚異の世界」なんていう番組があって、子供心に、驚嘆と共に、世界の奥深さを知ったものだ。
■ すばらしい世界旅行
■ 知られざる世界
■ 驚異の世界
当時、飛行機もすでにジェット機による国際便が飛んでいたわけだけど、ヨーロッパに行くにも、アラスカのアンカレッジを経由していた時代で、そんな中で、アマゾンやアフリカ、中近東など、海外というだけでも、とても遠いところで、庶民には一生縁の無いような世界だった。
現代のようにインターネットでつながっている世界ではないし、グローバリズムもないから、地球上の地域地域がそれぞれに独特の文化を持って暮らしていた。
1970年に開かれた、日本で初めての国際万国博覧会、大阪万博の映像なんてみても、各国の特色が色濃く出ていて面白い。当時、万博のパビリオンよりも世界中から集まった外国人を新鮮な目で見ていた人も多い。
最近では、タレントが毎週のごとく世界中に足を運び、3日〜5日くらいの弾丸取材でアフリカに行ったり、ブラジルに行ったりと、体力勝負で取材してこれるほど、世界は小さくなった。いろんな番組で、世界中の秘境と言われるようなところにも、軽々と取材班が入り、バラエティとして紹介されるほどだ。
僕自身、秘境とまでは言えないけれど、結構へんぴなところも旅してきたけれど、モンゴルの奥地で遊牧民の家族にお世話になったとき、彼らは大草原で、普通に携帯電話を持って、馬に乗りながら話しているのを見て、ここに来た意味があったのかと戸惑ったほどだ。
ゲル(テントの家)ではソーラーパネルで発電し、大きなパラボラアンテナで衛星放送を見て、なんと冷蔵庫まで持ってる。ただし、夜は電気が切れるのだが・・・
まあ、アフリカのマサイ族だって、携帯電話を持ている時代だから、もう未開の地なんてどこにもないのだろう。あるとすれば、深海くらいか。。。
今回のインタビューの雄己が紹介してくれているタイガは、これまでの日本からすれば、ある意味で未開の地に近かったのではないだろうか。しかし、驚いたことに、東京からの直線距離だと、北海道と変わらない距離にある大自然だ。それでも、実際のアクセスには一苦労するのだけれど・・・
この極東ロシアの地、タイガ地方は、ほとんど手つかずの森で、そこにいるのは、野生動物と先住民たちだけだ。もちろん、インタビューに出て来るように、先住民族の人々は、ソビエト時代に、ソ連化させられて、今もロシア的、近代的な暮らしをしている。しかし、村から一歩外に出ると、体長3メートルのアムールトラが、足音も立てずに存在を森に溶け込ませて、じっと侵入者を見ているような場所。そこは、人間のテリトリーではなく、大自然の掟が支配する神々の場所でもある。
人間は、神々の世界を忘れかけている。神々の世界では、人間のつくったルールなんて通用しない。そこには、大自然の摂理、神々の掟しかない世界。人間が作った世界は、神々の土台の上に作られていることを忘れてはいけない。神々が、くしゃみをすれば、その上に作られた世界なんて、一瞬にして吹き飛ばされてしまうのだ。
雄己が伝えてくれる大自然。そこに息づく人々の世界。本来人間に備わっている感性。生きる力。世界中に秘境なんてなくなってしまったこの時代に、神の掟が支配する本当の大自然は、村を一歩出たところに存在する。いや、神の掟は僕たちの魂の中にあり、本当の秘境は心の中にあるのだろう。
こうして僕たちが失いかけている世界を知ることで、僕たちの心の中にある大切なものをもう一度、思い出そうとしているのかも知れない。