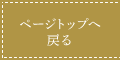| 中野: |
前半の最初の数字で表された状況を見たら「うわぁ!こんな世界が」、それで後半は「自重しなきゃ」って思う人もいるでしょうね。 |
| 和田: |
あとは怒りもありますよね。例えば、先ほどの世界の富の半部がって言うのを聞いても、何とかならないのかと思ったりとか |
| 中野: |
あります、あります。
「何とかしなきゃ」って言う人もいるかもしれない。 |
| 和田: |
ちょっと興味深かったのが、89人が異性愛者で、11人が同性愛者ってことで、10人に一人くらいは、同性愛者だっていうのは、すごく多く感じたんです。 |
| 中野: |
そうですね。これは、最初に訳して、皆さんにコピーを回した時に、反応する方が多かったですよ、日本では・・・ |
| 中野: |
10年前は、まだまだこういう新しい動きができていなかったですから、今はもういろんな考え方で生きている人たちが、堂々とカミングアウトしてますけど、当時はビックリされましたね。
でも、世界では、こういう人たちがたくさん集まっているオープンなところ、結婚もできるところがあるっていうことを知るだけでも「へー、いろんな所があるんだな」って思いますよね。 |
| 和田: |
そうですね・・・50人が栄養失調に苦しんでいるとか、80人が標準以下の居住環境であるとか、70人が文字が読めないとか、世界の状態が具体的にわかりますね。 |
| 中野: |
私たちって、自分が生まれて住んでいるこの環境で、全ての物差しを作っちゃいますよね。 |
| 和田: |
そうですよね。 |
| 中野: |
私は、今まで13年間外国で住んだ経験があるんですが、最初に、18歳の終わりにイギリスに行って、イギリスは結構長くて9年間住んでいました。その間、学生だったり働いたりもしました。近々は、ワシントンDCにある世界銀行で4年働きましたが、世界に出ると驚くことがいっぱいありました。
まず最初に驚いたのは、イギリスの語学学校に行って世界地図を見た時。日本で見慣れた地図とは違っているので結構ショックでしたね。 |
| 和田: |
そうですね。欧米は大西洋を挟んでヨーロッパとアメリカ、アフリカが中心ですよね。 |
| 中野: |
ええ、日本は日出る国ですから一番右端にあるんですよ。日本で見る教科書の地図では必ず真中にあったので「うわぁ!日本がない」って驚いちゃいました。南半球のオーストラリアの地図ではアップサイドダウンですよね。今度は日本が逆立ちしている感じなんです。それを見るだけでも驚きますよね。 |
| 中野: |
私は1993年から世界銀行で人事マネージャー、後にカウンセラーとして働きましたが、そこでは137カ国の人たちと一緒に働くんですよ。 |
| 和田: |
世界銀行は、国際機関ですね。 |
| 中野: |
世界の中から貧困を無くす金融の国際機関です。 |
| 和田: |
当時、世界の中で加盟している国でスタッフを送っているのが137カ国。世界銀行というひとつの屋根の下に、さまざまな国籍の職員が同僚として働いている。 |
| 和田: |
すごいことですよね。 |
| 中野: |
私は日本とイギリスを知っていましたし、その他の英語圏もある程度知っていましたけど、それ以外は初めて接する人たちもたくさん。宗教で言えば、キリスト教圏、イスラム教圏、仏教圏とか全く異なる宗教観を持つ人たちが、チームを組んでひとつの仕事をするんですよね。それはまるでオリンピック村で仕事をしているみたいでしたね。 |
| 和田: |
やはりイスラム系の人は、時間が来たらいきなりお祈りをするんですか? |
| 中野: |
はい。でもいつもじゃないですよ。ラマダンという時期がありますよね。ラマダンはお日さまが上がっている時はイスラム系の人たちは飲みも食べもしない。
世界銀行の中には地下に瞑想室があるんですが、二つ部屋があって、みんな好きな時に行ってヨガをやったり、瞑想したり、座禅を組んでもいいんですね。だけどラマダンのように特別な時は、一つは、イスラム教の人たち専用になります。そこで、一日に何度もメッカの方向に向かって祈るとかやってらっしゃいましたね〜。 |
| 和田: |
やっぱりそうですね。 |
| 中野: |
私はある時、皆さん忙しいからランチタイムに会議しようと思って、秘書さんに「このメンバーを集めてください」と頼みました。 茶色い紙袋に入ったお弁当やランチ持参で集まって、ミーティングする“ブラウン バッグ ランチ”です。そうしたら秘書さんが「今ラマダンなので、この人とこの人がメンバーに入っているのはちょっとまずいですよ」と。「そっかー、じゃあブラウンバックじゃなくて食事時間を終えてからミーティングだけしましょう」とかそういうことがありましたね。 |
| 和田: |
日本人どうしでも、人間関係では、「あの人にこう言われた」とか、自分のちょっと不快な気持があったりすると、当然、自分の感情が高まったりしますよね。日本人という文化的な価値観はある程度共有しているはずなんですけど、そういうところに行くと137カ国の人がいて、全部違う価値観をもっていますね。 |
| 中野: |
違いますね。私が人事カウンセラーをやっていた時は、私のクライアント1500人の個人データが私のコンピュータに全部入っていてロックされているんですけど、カウンセリングの予約が入った時にそのデータを取り出します。 ある時、調べてみたら1500人のクライアントの国籍は90カ国でした。クライアントのデータを見ながら「この国はどこにあったけ?」なんてあわてて世界地図で探すこともありましたね。 |
| 和田: |
うーん、全く文化圏が違いますね。 |
| 中野: |
違うでしょー。そうすると、私の感覚でその人に接して握手を求めてもいいのか、あるいはハグするのがフレンドリーの象徴なのかわかりませんよね。 |
| 和田: |
そうですね。ロシアの人だったら、顔を近づけてということも・・・ |
| 中野: |
あります、あります。世界銀行に働き始めたとき、受けなければいけないトレーニングがいくつかあって、その中にダイバーシティ・トレーニングというのがあるんです。
ダイバーシティ=多様性のトレーニングの中でビデオを見ながら「世界にはこんなにいろんな人がいます、信じているものも、考え方の基盤も違います。だからお互いを理解しましょうね。それで仕事をしましょうね」という内容です。
私はそれを見て、混乱したんですよ。だって90カ国の人たちの特徴を勉強するほど文化人類学者じゃないですもん。違いを見て考えていたらすごく悩んでどうしようと思ったんですね。 |
| 和田: |
ええ。 |
| 中野: |
だから、違いを理解することをあきらめて、私は反対に共通項を見て人と付き合うことにしようと思ったのです。私の世界観はそこにあるんです。
日本人だって同じ国民であってもそれぞれ地方によって違いますよね。私の好きなテレビの番組にケンミンSHOWというのがあるんですが、その県によって全然違って、その県を出たことがなければこれを常識と思っている。でも出てみると違う。違いを知ることは面白いけど、違いを知って、どうやって相手に対応しようかとピリピリするよりは、共通項は何かということを見る。取りあえずは日本人とか、あるいは地球人っていうように。世界中の人の究極の共通項は何だかわかります? |
| 和田: |
ん〜・・・なんだろう・・・ |
| 中野: |
世界中の何十億という人の共通項は、 |
| 和田: |
呼吸をすること・・・汗 そういうことじゃないですね・・・笑 |
| 中野: |
いいですね。生理的欲求があるということは、多分人間だからほとんど似ていますよね。だけどもう一つ時間的なことがあって、限りのある命を生きているということは共通なんですよ。 |
| 和田: |
なるほど。 |
| 中野: |
時期が来ると皆死ぬんですね。それはここで言うところの、白人であろうが黒人であろうが、宗教を信じていようが信じていまいが、生まれた時に地雷が埋まっている国に生まれようがなかろうが、つまり生まれた以上、全員が死ぬっていうことですよね。だから、死ぬまでにどう生きるかということが重要だと自分の考えがどんどんシフトしてきています。 |
| 和田: |
なるほどぉ〜。例えば、僕は幕末にすごく興味があって、中学三年生の時に見た大河ドラマで、明治維新の最中に翻弄する二人のサムライの物語なんですけど。
当時の交通機関って馬くらいしかないから、基本歩くしかなくて、地方文化の違いというのが、ものすごく差がありますよね。
例えば、全く違う文化の人たちが集まって、明治政府というものを打ち立てて、これからの時代は、薩摩も会津もないんだということで、理想を掲げて国づくりをしていくんですが、それだけでも価値観が大転換して大変だったと思うんですよ。
そういう時代の少し前に、ここ下田に、ペリーが黒船でやって来て、その時代に見た、生のアメリカ人っていうのは、一般の人たちからしてみれば、宇宙人を見たような、とんでもないショックだったと思うんですよ。 |
| 中野: |
そうですよね〜・・・・ |
| 和田: |
今でこそ外国というのは当たり前だし、日本人もたくさん出ていくし、外国人も日本に来て住んでいますけど、それで、世界というものを、知ったような気になっているんですよね・・・ |
| 中野: |
これからの時代のキーワードって何かって言うと、多様性のなかの調和なんですね。
同じ人たちが集まって、仲良しクラブを作っているところは、確かに楽に見えますが、そこに切磋琢磨するエネルギーとか、お互い違う人どうしが醸し出す化学反応がなければ面白くないんですよ。だからこそ、これからの世の中を面白く生きていくためには、多様性に強くなることが大切。 |
| 和田: |
面白いですねー・・・実は、カナダの人類学者で民族植物学者、冒険家というウエイド・ディビスという学者さんがいるんですが、彼のドキュメンタリーが以前、ナショナル・ジオグラフィックのTVプログラムであって、彼が世界中の先住民族の地を旅しながら、近代化に直面する文化と人々の暮らしに光を当てる番組だったんですが、グローバリゼーションが進むと世界は駄目になってくるということを言ってるんです。
例えば、アマゾン周辺には、昔3000もの言語があって、それだけ異なる部族がいたということですが、それが現在はわずか200くらいになっているらしいんですね。それで、面白い事に言語が3000あった時に比べて、今アマゾンの自然は激減しているんです。3000あった言語が200にまでなったというのは、当然淘汰されたり、いわゆるブラジルという国が統合されて、近代化による言葉や文化的な統一が図られてきたわけですよね。 |
| 中野: |
それ、興味深いですね。 |
| 和田: |
ブラジルという国家の価値観や考え方、思想というものが与えられ、統合されていって、言語が公用語中心になってくるわけですけど、そうすると何が起こったかというと、自然が非常にダメージを受けてることになっている |
| 中野: |
え〜面白い、なぜかなあ。 |
| 和田: |
結局それは何かな〜と思っていたら、部族がたくさんあるから、その部族同士が互いに境界線があり、争いを避けるために、ある程度、住む場所は限られるわけです。そうすると、その限られた世界の中を保とうとすることを彼らはやりますよね。 |
| 中野: |
はい。 |
| 和田: |
実は、それによって自然が保たれていたというんですね。その多様性がものすごく重要だと言っていて・・・ |
| 中野: |
ほんと、多様性は重要ですね。残念ながら日本って多様性に強い教育をされていないんですよ。 だって、私たち日本人は単一民族って簡単に言っちゃいますけど、本当は、その中にはいろんな人たちがいますよね。アイヌの人たちもいれば、南方系の人も、、、そういうことに対してみんなが同じだって言うと安心する国民なんですね。それで外国人が入ってきたり、あるいは帰国子女が入ってくると、学校でその人たちを仲間外れにしたりする。こういうのは、私たちには、多様性があるから世の中が益々面白いっていうことを、積極的に教える教育を必要としていないからじゃないかなって思うんですね。
私は、いろんな会社で企業コンサルをしますけど、仲良しクラブの様な会社って、みんながなーなーになっちゃうんですね。それでイエスマンばっかり集まった会社って危ないんですよ。だけど、みんなが違っていて、その個性をお互いに認めて活かしあって、そこから新しいものを作っていこうとするなら会社も伸びるだろうし、自分個人としても人生が面白くなるだろうな〜って。そこにはとても大切なことがあるんです。それは一人ひとりが今の等身大の自分にOKが出せるか出せないかっていうことがポイントなんですよ。
自分にOKが出せない人って、人にもOKを出さないんですよ。だから、人に対して自分と違うと責めてみたり、人を攻撃してつぶしたりするってところがある。でも自分にOKを出している人って、他人が違っていても、それを面白がる、興味深く知ろうとするっていうところに、進化のエネルギーが生まれると思うんですよね。どう思います? |
| 和田: |
そうですね、そう思います。 |
| 中野: |
うん・・・だからこそ、こどもたちには、一人ひとり違いがあるから面白いっていうことを教えたいって思うんですね。
 |